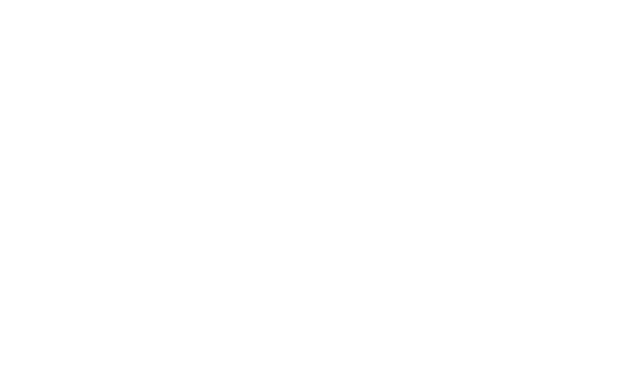ラッシュフォード「僕が伝えたいこと」
マーカス・ラッシュフォードは、『The Players' Tribune』に寄せた真摯な言葉の中で、マンチェスター・ユナイテッドに対する変わらぬ愛と情熱を強調している。
「Who I Really Am」(本当の自分)と題された長文の中で、26歳となったアカデミー卒業生は、自身のキャリアを取り巻く最近の話題について、率直かつ正直に語っている。ラッシュフォードは、自分がミスを犯したことを認め、責任を負うとしながらも、レッズへの献身性を疑問視されたときには声を上げるべきだと語っている。
ここでは、いくつかの注目すべき部分を紹介する。
「自分のアイデンティティを疑われるようなもの」
「僕は普段、自分について言われたことに反応するのは好まない」とマーカスは語り始めている。「それは僕の性に合わないんだ。僕は内向的な性格で、本当によく知っている相手以外には、自分のことを話すのも好きじゃない。だから、99%の場合はそうした雑音は無視できる。でも時々、ある一線を越えてしまうことがある。そういう時には、みんなに僕という人間をわかってもらいたいという気持ちになる」。
パンデミック以来、時に不当なスポットライトを浴びてきたことについて、マーカスは仕方のないことだと受け入れてはいるが、根も葉もない嘘は受け入れられない。
「僕は完璧な人間ではない。間違いを犯したら、真っ先に手を挙げて、改善することを誓う。でも、もし僕のマン・ユナイテッドへの忠誠心が疑われるようなことがあれば、その時こそ僕は声を上げなければならない。それは僕のアイデンティティや、人としての在り方すべてを疑われるようなものだからだ。僕はここで育った。少年の頃からこのクラブでプレーしてきた。僕がこのバッジを胸につけてプレーするために、僕が子供の頃、家族は人生を一変できるような大金さえも断っている」。
Few things I would like to say … https://t.co/aSqm8m3TXJ
— Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 29, 2024
「ユナイテッドでプレーするのが夢だった」
ラッシュフォードは、ザ・クリフでのトレーニングのためにマンチェスター中を4台のバスを乗り継ぎながら移動した、夢を追い求めていた子供時代を振り返り、そのすべてが価値のあるものだったと語っている。
「ユナイテッドが僕にとってどういう存在かを話し始めたら、みんなは僕のことを変人だと思うだろうね。僕自身でない限り、それはフェイクに聞こえるに違いない。でも理解してほしいのは、若かった頃の僕にとって、ユナイテッドでプレーすることがすべてだったということだ。それは手が届かないようなことだった。そこに入るのは大変だけれど、そこで続けていくのはもっと大変だった。僕が子供の頃、マンチェスターではあちこちで5人制の大会が開かれていた。参加する選手は全員1ポンドを支払うことになっていて、全ての年齢が対象だった。だから大人と対戦している子供たちもいた。トーナメントを勝ち抜けば、チームに賞金が入る。だから僕はいつも母親に1ポンドをせがんで参加していた。賞金は、オールド・トラッフォードのチケットが買えるくらいの金額だった。僕たちは若いチームだったけど、実際に何度か優勝したんだ」。
「僕にとっては、そこにいることがすべてだった。スタジアムがほとんど空っぽになって、みんながいなくなるまで、ただぼんやりと周りを見て、耳を傾けていたものさ。オールド・トラッフォードは本当に良い音がするんだ。まるでサラウンドエコーシステムがあるみたいな感じで、心が落ち着くんだよ。引っ越しすることが多かった子供にとって、ここはいつも自分の家のように感じられた。何かが自分の中にあるような...それは自分の中にあって、誰かが置いたものじゃない。ただそこに存在しているものだった」。
“The stuff that gets written about me — 90% of it is false. The problem is when people start to believe them.”
— Players' Tribune Football (@TPTFootball) February 29, 2024
Marcus Rashford opens up on his journey, the media and his hopes for the rest of the season. pic.twitter.com/HCILy8ia5c
「僕の中にハングリー精神が芽生えた」
この後ストーリーは、10歳のマーカスが、家族にとっては喉から手が出るほどの、生活を一変できるような金額を提示されたながらも、ユナイテッドでの夢を追い求めるためにそれを断ったことに話が及ぶ。
「お金は素晴らしい。幸せをもたらしてくれる。でも夢は、お金の価値では測ることのできないかけがえのないものだ。僕にとっては、11歳のときでさえ、ユナイテッドでプレーすることが唯一の目標だった。その頃のことで、今でも覚えていることがある。まだ契約をもらおうと必死だった頃、ワッツァ(ウェイン・ルーニー)とクリスティアーノ(・ロナウド)が何かをするのでアカデミーの若者たちのところにやってきた。彼らはカメラマンを連れていて、最後に僕たち全員が彼らと写真を撮るチャンスがあったんだけど、僕はみんなから離れた後ろの方にいたんだ」。
「僕は兄さんから、『何してるんだ?ワッツァと写真を撮ってこい!』と言われたんだけど、僕は『写真はいらない』と言った。
兄に「写真はいらないのか?と聞かれて僕は答えた。
「僕はいつか彼らと一緒にプレーするから」って。
写真を撮らなかったのは僕だけだったと思う。高額のオファーを断った後、僕の中に、ハングリー精神が芽生えていた。もう自分が子供だとは思えなかった。チャンスをつかんで自分たちの人生を変えなければならないと思った。ハルムやモスサイド、チョールトン、ウィジントン、ワイセンショウ......マンチェスター近郊で生まれ育った子供にとって、それは夢を叶えるための生き方だ。僕が当然のようにそれを手に入れたと思っている人がいたとしたら、それは僕のことをまったくわかっていない、ということになる」。
「フットボールはバブルのようなものだ。僕は普通の人でいようと努力してきた。同じ友だちとの付き合いも続けている。夜遊びしているときやホリデーの間も、なるべく変わらないようにしてきた。でも、それとは別の側面もある。僕は人間だ。20代の若者の多くが犯すような過ちだって犯���し、そこから学ぼうとしてきた。でも、僕は同時に、誰も知らないような犠牲も払ってきた。みんなに理解してほしいのは、苦しい時にプレーを続けさせてくれるのはお金ではないということだ。それはプレーへの愛でしかない。単純明快にね」。
“I treat United the same way I treat my family.”
— Players' Tribune Football (@TPTFootball) February 29, 2024
For Marcus Rashford, Old Trafford is home. ❤️ pic.twitter.com/xdNxxWgDv6
「僕は今でもファンの一人」
「ここ数シーズン、このクラブが過渡期にあることは誰もが知ってのとおりだ。僕たちが勝っているとき、みんなは世界で最も偉大なファンであり、それは事実だ。クラブにはもっと昔ながらのポジティブなエネルギーが必要だ。あのような雰囲気が何をもたらすかを僕は知っている。自分が最悪の状態にあるときでも、頑張り抜く力をくれるんだ。ピッチに出て、ファンが僕の名前を歌ってくれるのを聞くたびに、そしてキックオフの前にオールド・トラッフォードを見渡すたびに、僕は同じポジティブなエネルギーを感じている」。
「心の奥底では、キックオフの時に周りを見渡すときの自分は、まだファンの一人なんだ。その気持ちが今でも忘れられない。初めてアンフィールドでプレーした時、ユナイテッド対リヴァプールのあの雰囲気をピッチから感じて、ホイッスルが鳴って観客の歓声を聞いた時、アドレナリンが出すぎて試合開始早々に退場になりそうになったこともまだよく覚えている。僕はジェームズ・ミルナーが大好きで、彼に向かって突進してしまって非情なタックルに及んでしまった。あまりに自分の中から感情が湧き上がりすぎて、そんな行動をとってしまったんだ。それはユナイテッドの選手としてではなく、たまたまリヴァプール戦のピッチにいた一人のユナイテッド・ファンとしての行動だった。家に帰って、家族に『今すぐなんとかしなくちゃいけない。自分の中からファンである部分を消去しなくちゃ。でないと、毎試合で退場処分を食らうことになる』って言ったのを覚えているよ」。
「どんな批判も受け止める。どんな見出しでも受け止める。ポッドキャスト、ソーシャルメディア、新聞、僕は受け止めるよ。でも、このクラブに対する僕の忠誠心やフットボールへの愛情を疑うようなことだったり、家族を持ち出すようなことがあったら、シンプルに、もう少し人間的な対応をしてほしいとお願いする」。
“We need to figure out a way to take part of me as a fan out of it.”
— Players' Tribune Football (@TPTFootball) February 29, 2024
Marcus Rashford looks back on his first game at Anfield and how he was almost sent off. pic.twitter.com/UUMsuzxQIZ
「自分たちがいるべき場所に戻る」
ラッシュフォードの長文は、自身とチームに対する力強い意思表示で締めくくられている。「肉体的、精神的に落ち込んだときはいつも、これは転換期であって、ユナイテッドとイングランドのために最高のフットボールをするときだと感じている」。
「約束するよ、世界はこのユナイテッドのチームと選手たちの最高の姿をまだ見ていない。チャンピオンズリーグに復帰したいし、そうなれば、シーズン末にはビッグな国際大会に臨める。自分たちがいるべき場所に、僕たちは戻る。そのために努力し続けるだけだ。そして、それは僕自身から始まる」。
「僕を支持してくれるなら、ありがたい」。
「僕を疑うなら、なおさら良い」。
記事全文は『The Players' Tribune』で。